地方と中央の格差
わが国では民主国家といえども、中央集権主権的な風土が強い傾向にあると言えるでしょう。江戸時代、地方で行き詰って江戸に出るという話は聞きました。
富と権力が集まっている中央でひと肌上げようと飛び出した人々は大勢いたことでしょう。人手不足の時はコネや経歴よりもやる気だったことでしょう。
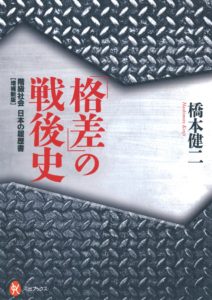 未発達状態では中央と地方の格差が激しく、ここ50年前まではかなりの大差であったことでしょう。かつて、中央から遠い地方は後進県、発展途上県などと一時、呼ばれていました。
未発達状態では中央と地方の格差が激しく、ここ50年前まではかなりの大差であったことでしょう。かつて、中央から遠い地方は後進県、発展途上県などと一時、呼ばれていました。
プロ野球は主要都市にしか存在せず、ナイター設備のある地方球場は皆無でした。今では北海道、東北地方にも球団が存在しています。
Jリーグのサッカーチームは結構、あちらこちらにあるのに対して、プロ野球チームはまだ、中央寄りです。北陸、山陰、四国地方辺りにプロ野球の球団がないのはさみしいです。
地方の追い上げと限界
発展している地方都市に出かけるとセブンイレブン、ドン・キホーテ、イオンなどの店が目白押しで似たような景色に出会い今、どこにいるのかわからない時があります。
人が集まり購買力があるからこそ、出店が続いているのでしょう。中に入ると店の雰囲気がどこも変わっていないことに気づきます。中央の仕組みがそっくり乗り移っているかのようです。
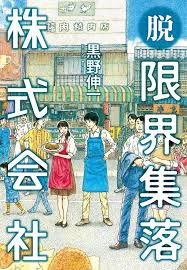 地方都市では周辺人口を飲み込むかのように人が集まっているようです。その一部では限界集落が増えていることでしょう。また、公共施設や商業施設の建築ラッシュでにぎわっていても、成熟した数十年先の青写真が明確になっているのでしょうか。膨れ上がった風船はいつか破裂します。
地方都市では周辺人口を飲み込むかのように人が集まっているようです。その一部では限界集落が増えていることでしょう。また、公共施設や商業施設の建築ラッシュでにぎわっていても、成熟した数十年先の青写真が明確になっているのでしょうか。膨れ上がった風船はいつか破裂します。
石油に頼っているある中東国では、やがて石油が枯渇した時を見越して資源小国の日本に学ぼうと先刻、役人が大挙して来日しました。
登りつめた先に、古くなった公共施設の維持もできなくなって廃墟都市にならないとも限りません。将来に負の遺産を残して見かけ上の発展には気を付けましょう。持続可能な発展(Sustainable development)が望まれます。